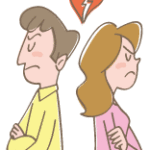
1 婚約と慰謝料
婚約している人と第三者が不貞をすると慰謝料が発生する可能性があります。
また、婚約を不当に破棄した人は慰謝料支払い義務を負います。
しかし、どのような段階になったら婚約が成立したと言えるのか、必ずしもはっきりしません。
そこで以下、裁判例を参考に、どのような場合に婚約が成立したと言えるのか、見ていきます。
2 婚約の成否についての裁判例
東京地裁令和4年1月28日判決
「原告は,同年6月又は7月頃,被告Y1との同居を開始し,この頃から被告Y1との間で定期的に性交渉を行うようになり,同年10月17日,妊娠を知り,同月○○日,被告Y1に対して妊娠を報告したことが認められるが(前記前提事実,甲44,乙21,被告Y1本人),本件全証拠に照らしても,同年9月までの間及び原告の妊娠が発覚した同年10月以降のいずれにおいても,原告及び被告Y1が,婚姻の届出の時期及び方法に関する具体的な打合せ,結納の実施(又は不実施の合意),婚約指輪の購入(又は購入しないことの合意),結婚指輪又は結婚式の要否,時期,場所及び方法等に関する具体的な打合せ又は下見並びに双方の親への挨拶等の婚約を示唆する行動をした事実があったとは認められない。したがって,原告と被告Y1との間に婚約が成立したと認めることはできない。」
東京地裁令和3年9月7日判決
「原告と被告が東京都内のホテルでウェディング担当者と少なくとも挨拶をしたことがあったとしても,具体的に式の日取りを決めたり,見積を取ったなどといった事情も認められないことからすれば,原告と被告との間に,婚約が成立していたことを推認させる事情ではない。さらに,交際相手の一方が他方に自身の氏と交際相手の他方の名を組み合わせた印章を贈ることが,婚約指輪を贈ることほどに婚約の象徴的な意味合いを有しているという社会通念が確立しているということはできないことからすれば,原告が被告に対して「Y1’」の印章を贈り,被告もこれを年賀状に使用していたという事情は,原告と被告との間に婚約が成立していたことを推認させる事情ではない。また,原告と被告とが互いに両親を婚約者として紹介することについて支障があることを示す事情もうかがわれない以上,原告が,被告の両親と面会したことがなく,被告を原告の両親に会わせたことがなく,原告の両親に被告と婚約したことを告げることもなかったという事情は,原告と被告との間に将来的に婚姻をするという確定的な合意が成立していたことに疑問を生じさせる事情であるということができる。」として婚約の成立否認
東京地裁令和3年8月19日判決
「互いの親族や友人等に対する紹介や婚姻する予定であることの報告,結納や婚約指輪の交換,結婚式の準備,共同生活やそれに向けた準備等がされたとの事実は認められず,原告と被告との交際関係が婚姻を前提とするものであったことをうかがわせる外形的な事実は存在しないといわざるを得ない。」
東京地裁平成30年2月22日判決
「原告とAとは,同年11月には婚約したとしながら,そこから2年5か月が経過した平成26年4月15日になって入籍していること,証拠(乙1,原告本人・11頁)によれば,被告とAとの関係が原告に判明したという同年2月の時点においてすら,具体的な婚姻の日取りは決まっていなかったこと,原告は平成20年5月以降東京都豊島区内に住民票があり,Aは原告と結婚するまでの間,茨城県内に住民票があったことが認められ,これらの事実に照らすと,法的保護に値するような婚約又は同棲の状況があったとは認め難い。
東京地裁平成29年10月30日判決
「原被告間における婚約の成立をうかがわせる客観的な証拠は,本件申込書のみであるほか,被告が指摘するとおり,原被告が結納や結婚式場の下見,婚約指輪の購入などをしていないことは,当事者間に争いがない。」→婚約否定
東京地裁平成28年11月14日判決
「被告Y1は,後記のとおり,平成20年12月頃に,原告に対し,婚約指輪を渡し,原告と被告Y1が,平成21年2月ないし3月頃にはそれぞれの親が参加する顔合わせの食事会を行っていることなどからすれば,原告の主張に沿う証拠(原告本人1,20頁)は信用することができ,これによれば,原告は,被告Y1から平成20年9月頃に離婚が成立したら結婚しようと言われたことが認められる」→婚約肯定
東京地裁平成27年11月17日判決
「原告は,平成24年8月8日,被告Y1と婚姻する意思で被告実家に転居しており,被告Y1も,原告及びAを実家に迎え入れて同居を開始していることからすれば,遅くとも,同時点で原告と被告Y1との間で婚約が成立したと認められる。」
これらの裁判例からは、ⅰ 入籍があった場合はそれまでの期間、ⅱ 婚姻の日取りの決定の有無、ⅲ 住民票や同居の有無、ⅳ 結納や結婚式の準備、ⅴ 婚約指輪の授受、ⅵ 親を交えての集まり、ⅶ 結婚をするとの意思表明などが総合考慮され、婚約の成否が判断されていることがわかります。
決して結婚を約束したという一事だけで婚約成立とはならないことに注意が必要です。
3 婚約破棄の慰謝料額
東京地裁令和2年2月17日判決は、
(1)慰謝料について 100万円
(妊娠中のタイミングで婚約破棄したため、出産せざるをえなかったこと考慮)
(2)医療費について 20万6630円
(妊娠、出産に伴うもの)
(3)得べかりし利益について 130万円
(妊娠、出産により就労できなかったことに対応するもの)
の賠償を認めています。
東京地裁平成30年2月27日判決は、「原告と被告との共同生活は10年以上に及び,その間,原告が,被告の生活費やDへの婚姻費用の支払など種々の事務を行い,それに伴い,後記で検討する通り,相当な出捐をしてきたことなどからすれば,原告の精神的苦痛も小さいとはいえ」ないとして、慰謝料100万円を認めています。
東京地裁平成28年11月14日判決は、「原告は,被告Y1の子を出産して被告Y1と婚約したこと,原告は,被告Y1から婚約の解消の申出を受け,原告と被告Y1の関係は必ずしも強固なものとはいえなくなったこと,被告Y1は平成24年11月頃,一旦は婚約破棄を撤回した後も自己の保身のために再び婚約を破棄するに至ったこと,被告Y1は調停が申し立てられるまでGの認知を拒んだ」等として、慰謝料150万円を認めています。
東京地裁平成28年11月1日判決は、
・婚約中にも関わらず複数異性と交際等したため婚約関係が解消したので悪質性が大きい
・交際2か月で婚約成立、その1か月後に婚約解消という交際・婚約期間の短さ
・結納をしておらず,結婚式場の予約もしていなかった
等として慰謝料50万円を認めました。
その他、指輪代から地金の価値(1割)を分として、ダイヤモンドリングについては114万2100円,ペアリングについては42万2820円の賠償を認めました。
以上から、
・婚約破棄の慰謝料は数十万円から100万円が多い、
・100万を超えることがなくはない
・交際・婚約期間、婚約破棄に至った事情の悪質性、婚約を裏づける事情の強さ
・妊娠・出産など、婚約破棄のダメージの大きさ
等で慰藉料額が決まることが分かります。
4 新潟で婚約破棄、離婚をめぐるご相談は弁護士齋藤裕へ
もご参照ください。
離婚・婚約でお悩みの方は弁護士齋藤裕にご相談ください。
まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。
弁護士費用はこちらの記事をご参照ください。
さいとうゆたか法律事務所トップはこちらです。

