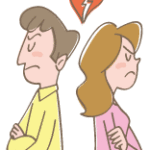
1 DV加害者からの離婚請求を認めた事例
有責配偶者からの離婚請求については原則認められないというのが判例の立場です。
不貞やDV,暴力が有責性を裏付けることは明白です。
しかし、ここでの有責性というのは一定程度高度なものが求められます。
よって、DVや不貞があったとしても、状況によっては有責配偶者と認められないこともあります。
例えば、東京地裁平成16年3月1日判決は、以下のとおり述べ、離婚を請求する側に暴力があったと認めつつ、有責配偶者とはせず、離婚請求を認めました。
同判決の認定する暴力は以下のとおりです。
「原告は,平成11年7月13日朝,被告が原告の父に原告が会社経理上の不正行為をしていることを告げたことに立腹し,本件家屋において,被告と口論となり,興奮して被告の手や足を蹴り,被告に右示指,右足首打撲,右前腕及び右肩挫傷による全治10日間の怪我を負わせた(乙1)。」
当該夫婦は平成11年6月に別居を開始しており、暴力は別居後ということになります。
また、同判決は、別居時ごろから原告が不貞をしていたことを認定しています。
このように一定の強度のある暴力や不貞がされたことが認定されています。
しかし、同判決は、以下のとおり判断し、有責配偶者からの離婚請求とはしませんでした。
「原告とAとの関係が,被告との間の婚姻関係の破綻を深める要因の一つになったことは否定できないものの,認定可能な二人の交際の時期は,前記のとおり,別居した後である平成11年以降であるから,上記関係が,原告と被告との間の夫婦関係を破綻させる大きな要因になったとは認められない。」
「また,原告が被告に対し平成11年7月13日に暴力を振るったことは前記認定のとおりであるが,その時期や状況などを考慮すると,この事実をもって直ちに原告を有責配偶者とみることは困難である。」
同判決が暴力や不貞の存在を認めつつ、有責配偶者とはしなかったのは、別居後に暴力や不貞があったということが一因と考えられます。
別居時点でただちに婚姻関係が破綻しているとはいえません。
それでも、別居したということは婚姻関係が破綻に向けて大きく動いたということを意味しますから、その後にあった暴力や不貞は婚姻関係が破綻するについて大きな影響力を発揮したとはいえないでしょう。
その他、一定の被害が生じた暴力であるものの1回であったことなどが考慮され、有責配偶者とはされなかったと考えられます。
有責配偶者からの離婚請求であるとの主張をする場合、一定程度悪質な事情があることが求められることに留意する必要があります。
2 新潟で離婚のお悩みは弁護士齋藤裕へ
もご参照ください。
離婚でお悩みの方は弁護士齋藤裕にご相談ください。
まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。
弁護士費用はこちらの記事をご参照ください。
さいとうゆたか法律事務所トップはこちらです。

