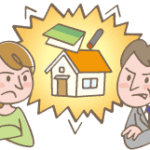
執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

相続、遺産分割のお悩みはご相談ください。
まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。
目次
1 公正証書遺言とそのメリット
1 公正証書遺言とそのメリット
遺産を自分の思いに従い相続させようとするには遺言書を作る必要があります。
この遺言書の中で代表的なものが自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言は自分で書いて、日付を書いて、署名・押印すればいいので、簡単です。カレンダーの裏に書いても一応有効です。自分だけでやるなら金もかかりません。
公正証書遺言は公証人役場で作ってもらうものですが、公証人役場に払うお金がかかります。
どちらがよいかですが、基本的には公正証書遺言が無難かと思います。
自筆証書遺言だと、そもそも遺言者が本当に書いたのかどうか争いになることがあります。また、遺言をする能力があったかどうか争われることもあります。
公正証書遺言でも後者の争いはありえますが、それでも自筆証書遺言に比べれば可能性はかなり小さいといえるでしょう。
相続が争続にならないようにするため、できるだけ公正証書遺言とすることをお勧めします。
2 公正証書遺言の作り方
公正証書遺言は公証人役場で作成します。
内容について弁護士のアドバイスを受け、その上で公証人役場で遺言書作成をすることが多いです。
公正証書遺言の作成方式については、民法969条が以下のとおり定めています。
一 証人2人以上の立ち合い
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと
五 公証人が、その証書が法律の定める方式に従って作成したものであることを付記し、これに署名し、印を押すこと
口授については、公証人が〇〇ですねと言い、遺言書が頷くという程度では要件を満たさないとされます(最高裁昭和51年1月16日判決)。参照:口授による遺言を無効とした判例
口をきくことができない人については、通訳人の通訳あるいは自書により口述に替えることができます(民法969条の2、1項)。
耳が聞こえない人については、公証人が筆記内容を通訳人の通訳により伝えることができます(民法969条の2、2項)。
3 公正証書遺言と遺言の効力
公正証書遺言における遺言能力の判断基準
公正証書遺言については、自筆証書遺言に比べ、その効力が争われたり、効力が否定されることが少ないとは言えます。
そうはいっても公正証書遺言についても方式をみたさない、あるいは遺言能力がないなどとして効力が争われることはあります。
公正証書遺言について遺言能力があるかどうかは、
ⅰ 認知症等の程度
ⅱ 遺言内容の複雑性
ⅲ 当該遺言に至ることが合理的と言えるか
ⅳ 筆跡の乱れなど
を考慮して判断されます。
自筆証書遺言と違い、公証人が一応遺言能力についてチェックすることから、自筆証書遺言に比べ遺言能力の点からも効力が否定されにくいとは言えるでしょう。
公正証書遺言における遺言能力が否定された裁判例
なお、東京地裁令和3年3月31日判決は、平成25年に作成された従来のすべての遺言書を全部撤回するとの公正証書遺言について、
・遺言者が平成23年にアルツハイマー型認知症と診断されたこと
・遺言において、遺言者が「半年位前より以前の時期のことについては、・・・よく記憶していませんし、よく思い出せません。ですから、ひょっとしたら、半年位前より以前に遺言書を作っているかもしれない気もするのです。しかし、自分でもはっきりしません」と付言していたこと
・平成24~25年にかけ、直前の出来事を失念する、ファックスの送信方法を失念する、物をなくす、男性なのに女性用トイレを使用する、造花に水をやる、近所で道に迷う、お金を払っていないのに払ったと勘違いするなどの言動があったこと
・遺言の撤回により様々な困難が生じること
・公証人において遺言能力確認のためにどのような方法をとったのか不明であること
などを理由に遺言能力を認めませんでした。
公正証書遺言における遺言能力が肯定された裁判例
京都地裁平成13年10月10日判決は、
・遺言者の痴呆が相当高度に進行していたものの,いまだ,他者とのコミュニケーション能力や,自己の置かれた状況を把握する能力を相当程度保持していたこと
・遺言を作成するよう思い立った経緯ないし動機には特に短慮の形跡は窺われないこと
・遺言の内容は比較的単純のものであったこと
・甲公証人に対して示した意思も明確なものであったこと
から遺言能力を認めました。
公正証書遺言と遺言能力について注意すべき事項
公正証書遺言だから常に効力が認められるわけではないことに注意が必要です。
弁護士のアドバイスを受けつつ、慎重に遺言能力の有無を判断し、場合によっては遺言能力を裏付ける証拠を残しておくことが大事です。
4 新潟で公正証書遺言のお悩みは弁護士齋藤裕へ
新潟で公正証書遺言、相続でお悩みの方は、弁護士齋藤裕にご相談ください。
まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。
弁護士費用はこちらの記事をご参照ください。
さいとうゆたか法律事務所トップはこちらです。

