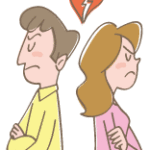
1 日常家事債務
夫婦と言えども、別人格ですから、夫の借金について妻、妻の借金について夫が支払う必要はないというのが原則です。
しかし、民法761条は、以下のとおり定め、日常家事債務の連帯債務を規定しています。
「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない」
この日常家事債務で、夫または妻が、他方配偶者の債務について連帯債務を負うという事態は、それほど広くはありません。
典型的には、日常生活にとって必要な食品、電気・ガス・水道、教育のための代金等が日常家事債務の対象となります(子どもの柔道の指導料について日常家事債務として認めた裁判例として横浜地裁平成28年3月31日判決があります)。
NHKの受信料についても日常家事債務に該当することを認めた裁判例があります。
ですから、例えば、妻が生協で食品を買って、代金を払わない場合、生協は夫に対して日常家事債務として請求をなしうる可能性があります。
また、数十万円レベルの買い物等については、買い物等のためのクレジット契約により生ずる債務についても、日常家事債務の対象となりやすいです。
他方、借金については、日常家事債務に含まれないのが原則と考えた方がよいでしょう。
家族の生活に必要な用途のために、数十万円レベルの借金をしたような場合であれば、日常家事債務となる可能性はあります。
夫が、子ども教育のために銀行から教育ローンで30万円の借金をした場合、妻もその返済義務を負う可能性はあります。
しかし、借金の金額が高額であったり、借金が家族の生活に必要な用途のためかどうか明確ではない場合、日常家事債務とは認められにくいです。
例えば、東京地裁平成15年8月26日判決は、「被告Y2が原告から150万円を借り入れた事実は争いがないが、この借入金が生活費のためであることを認めることはできないし、貸付金も高額であり、被告ら夫婦の日常家事債務と認めることはできないから、被告Y1が連帯債務を負うことはない。」と述べて、貸金の金額が150万円と高額で、借入金が生活費のためであったことも裏付けられないとして、日常家事債務であることを否定しました。
他方、東京地裁令和3年9月2日判決は、「本件の借入れは,認定事実(1)~(3),甲25~28に照らせば,被告らの家計(住宅ローン,子の教育資金等)の慢性的・恒常的な不足によるものであり,その貸付額も一回当たりの金額は高くとも150万円でほとんどは数十万円単位であったから,民法761条の日常家事債務として被告Y1の夫である被告Y2も連帯してその責任を負う。この理は,結果として貸付残額が高額となったことや,被告Y2が自らの意思で積極的に家計支出や家計管理に留意しなかったことによっても変わらない。」として、1回あたりの貸付額が数十万円であることがほとんどだったことを理由に日常家事債務であると認めました。
以上より、日常家事債務が成立する範囲は必ずしも広くはありませんが、少額の買掛などについては日常家事債務とされ、他方配偶者が請求されることもありうるので注意が必要です。
2 新潟で離婚のお悩みは弁護士齋藤裕へ
離婚全般についての記事
もご参照ください。
離婚、財産分与でお悩みの方は弁護士齋藤裕にご相談ください。
まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。
弁護士費用はこちらの記事をご参照ください。
さいとうゆたか法律事務所トップはこちらです。

