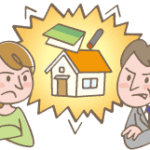
離婚の際には財産分与がなされることがあります。
この財産分与は大きく清算的財産分与と扶養的財産分与に分けることができます。
以下、
1 清算的財産分与
2 扶養的財産分与
4 財産分与についてのその他の事柄
5 弁護士費用
について解説します。
1 清算的財産分与について
清算的財産分与とは?
一般的にイメージされることが多いのは清算的財産分与だと思います。
これは夫婦の財産を離婚に当たり分けることです。
分与をする割合
通常は折半となりますが、一方配偶者が医師など稼働能力が高い場合、もともと資産などを有していた場合など、財産形成に与える影響が大きい場合にはそれ以外の割合で分与されることもあります。
例えば、福岡高裁平成30年11月19日決定は、「抗告人及び相手方の内縁関係が成立する前から,相手方は,不動産賃貸業を営む株式会社の代表取締役として,長年にわたって同社の経営に携わるなどして,相当多額の資産を保有していたこと,他方で,抗告人は同居前に破産申立てをするなど,内縁関係が成立する時点において目立った資産を保有していなかったこと,また,平成7年5月頃に内縁関係が成立した時点で,抗告人は57歳,相手方が60歳であったことに照らすと,原審判が説示したとおり,財産分与の対象財産の形成及び増加等について,相手方の保有資産及び長年築いてきた社会的地位等による影響や寄与が相当程度あったと認められるというべきである。これによれば,原審が説示したとおり,分与割合について,抗告人を3分の1,相手方を3分の2と認めるのが相当である。」として、婚姻前から資産を有していた側の取り分を3分の2としています。
浪費や使途不明金がある場合にも割合が折半とならないことがありえます(浪費、使途不明金がある場合と財産分与をご参照ください)。
共稼ぎであるにも関わらず、どちらかしか家事・育児を担っていなかったような場合、家事・育児を担当していた側の分与割合が高くなることもありうると考えます。東京家裁平成6年5月31日決定は、夫婦共稼ぎで、妻だけがもっぱら家事労働をしていたというケースで、妻と夫の寄与割合を4:6とみました。ただし、この事例では、妻の収入がかなり大きかったという事情はあります。
どちらかの親が実質贈与により財産形成に寄与している場合において、そのことが財産分与の割合において考慮されることもあります。例えば、東京高裁令和3年12月24日決定は、「本件における財産分与対象財産(夫婦の協力によって得た財産)の額には,抗告人の父母による支援の結果として形成された,夫婦の協力によって得たものとはいい難い財産が相当額含まれていることが認められる(実際に,抗告人の父が管理していた相手方名義の財産番号1の預金額だけでも,その額は約1800万円になる。)。そうである以上,相手方が求める本件の財産分与の判断においては,このような事情を「一切の事情」として考慮するのが,財産分与における当事者の衡平を図る上で必要かつ合理的であると認められるのであって,以上の事情(本件における基準時財産の額及び財産形成の寄与の程度,これらを前提とした上記(1)の算定に係る財産分与額)のほか本件に現れた一切の事情を考慮すると,財産番号1の相手方口座の預金を除く相手方名義の財産については相手方が取得することを前提に,抗告人に対して,本件の財産分与として2800万円を相手方に支払うように命ずるのが相当である。」として、親による実質贈与をも考慮し財産分与の割合を決めています。
財産分与の対象となる財産
財産分与に当たってはその財産の名義が誰のものであるかはあまり関係しません。夫婦が結婚してから共同で作りあげた財産については名義の如何を問わず財産分与の対象となります。
財産分与対象財産は別居時に存在した財産となります。
財産分与の対象となる財産があるかどうかわからない場合、その財産はないとみなされます。
例えば、福岡高裁平成30年11月19日 決定は、「基準日において財産分与の対象財産が存在することは,存在すると主張する方が立証責任を負うと解するのが相当であるところ,相手方は,抗告人がその存在を主張する動産類の存否についてひとつひとつ説明し,上記資産についても,「確かに購入したが,花瓶を移動する折に繊細な人形が割れてしまい破損した。」旨ある程度具体的な説明をしていること(乙46)も考慮すると,現在において上記資産が存在することをうかがわせる事情が見当たらない限り,これを財産分与の対象とすることはできない。」として、ある時点で存在していた財産がなくなったと主張されている場合について、なくなったことについて一応の説明があれば、その財産がないものとして扱うものとしています。ただし、なくなったことについての説明が不自然であったり証拠と矛盾していたり、財産があった時点と別居時点との間隔が短いような場合、なくなったとの説明があっても、その財産が存在している前提で財産分与がされる可能性はあるでしょう。
夫婦が共同で作り上げた財産が分与の対象になりますから、結婚前の財産は対象にはなりません。また、別居後の財産も分与の対象とはならないのが原則です(詳しくは特有財産と財産分与の記事をご参照ください)。
子ども名義の財産でも財産分与の対象となりえます(お年玉と財産分与についての記事をご参照ください)。
結婚前の財産については、記録がなく、それが結婚前からの財産なのか夫婦が築き上げた夫婦共有財産なのかはっきりしない場合もあります。そのような場合には夫婦共有財産として推定されることになりますので、結婚前から大きな財産を持っていた配偶者としては結婚時点における財産の記録を残しておくことが肝要ということになります。
別居後の財産については、例えば一方が他方に払うべき婚姻費用を払わなかったことによって蓄財したような場合、別居後の財産でも例外的に分与の対象となりうることになります。
注意しなければならないのは、財産分与の対象となるのはプラスの財産だけということです。
借金というマイナスの財産は分与の対象とはなりません(マイナスの財産も分与の対象になるという裁判例もありますが、あくまで少数です)。ですから、住宅ローンを負っている方の配偶者が、他方配偶者に対しローンを負担するよう求めることは原則としてできません。しかし、夫婦の生活のために借金をし(住宅ローンなど)、同時に夫婦間にある程度のプラスの財産もある場合、借金を背負う方がプラスの財産を取得するというように、プラスの財産とマイナスの財産を通算して分与方法を決めるということはありえます。
もご参照ください。
2 扶養的財産分与について
どちらかの配偶者が離婚後生活困難であり、他方配偶者に十分な資力があるような場合、扶養的財産分与として定期金の支払いなどが命じられることもあります。
しかし、これは十分な慰謝料や清算的財産分与がなされないような場合において認められるものであり、認められるケースは多くはありません。
詳しくは扶養的財産分与についての記事をご参照ください。
3 財産分与を求める手続き
財産分与を求める手続きとしては、交渉、調停、審判、離婚訴訟があります。
交渉で解決しない、あるいは解決しそうもないのであれば離婚調停や財産分与調停を起こし、そこで財産分与について話し合います。
財産分与調停で解決しない場合、審判に移行します。
離婚調停で解決しない場合、離婚訴訟を起こし、その中で財産分与について解決することになります。
財産分与の審判において、Xが財産分与を請求していたものの、逆に相手方であるYが請求でき、Xには権利がないという場合、YからXへの財産分与請求が認められる可能性があるので(広島高裁令和4年1月28日決定)、注意が必要です。
4 財産分与についてのその他の事柄
もご参照ください。
5 弁護士費用
当事務所の弁護士費用は以下のとおりです(消費税別)。
長引いたからといって着手金などを追加でいただくことはありません。
・初回相談料 無料
・離婚交渉 着手金5万円 報酬10万円(財産分与などで経済的利益があるときは、その10パーセントと10万円の大きい方)
・離婚調停 着手金20万円(交渉から引き続き受任した場合の着手金は15万円)
報酬20万円(財産分与などで経済的利益があるときは、その10パーセントと20万円の大きい方)
・離婚訴訟 着手金20万円(調停から引き続き受任した場合の着手金は15万円)
報酬20万円(財産分与などで経済的利益があるときは、その10パーセントと20万円の大きい方)
例 相手方が離婚も財産分与を拒否している場合
交渉の着手時に5万円をいただきます。
話し合いで解決しなければ離婚調停となりますが、その際着手金15万円をいただきます。
さらにそこでも解決せず、離婚訴訟をする場合、着手金15万円をいただきます。
最終的に離婚が成立し、300万円の財産分与が得られた場合、300万円の10パーセントである30万円が20万円より大きいため、報酬30万円をいただきます。
6 新潟で離婚のお悩みは弁護士齋藤裕へ
もご参照ください。
新潟で離婚のお悩みは弁護士齋藤裕にご相談ください。
まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。
弁護士費用はこちらの記事をご参照ください。
さいとうゆたか法律事務所トップはこちらです。

