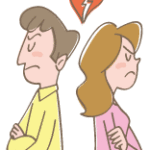
離婚前に夫婦が別居するような場合、一方が他方に婚姻費用と呼ばれる生活費を請求できることがあります。
この生活費は、裁判所の作っている養育費・婚姻費用算定表に従い算定されることが多いです。
日本弁護士連合会も同様の算定表を作っていますが、参考にされることはほぼありません。
具体的な婚姻費用算定については、
もご参照ください。
以下、婚姻費用請求について注意すべき点を述べます。
目次
1 婚姻費用請求の手続き
2 婚姻費用と住宅ローンの処理
3 婚姻費用と夫婦共有財産の持ち出し
4 婚姻費用の変更
5 弁護士費用
1 婚姻費用請求の手続
交渉により婚姻費用を取り決めることは可能です。
一旦書面などで明確に婚姻費用を取り決めた以上、それに従い婚姻費用を支払う義務が発生します。
交渉で取り決めることができない場合、婚姻費用を請求する調停を家庭裁判所に申し立てることになります。
この家庭裁判所は相手方居住地の家庭裁判所です。
調停で話し合いがまとまらない場合には調停は不調となり、審判手続きに移行します。
審判手続きでは、裁判官が双方の主張を踏まえ婚姻費用を定めることになります。
なお、婚姻費用は、調停申立てなどの請求行為があった月分以降の分が認められることが多いです。
内容証明郵便により請求した後について支払義務を認める裁判例もあります(宇都宮家裁令和2年11月30日決定等)。
もご参照ください。
2 婚姻費用と住宅ローンの処理
よく問題になるのが住宅ローンです。
住宅ローンを払っている配偶者がその家を出て、別途アパートを借りるような場合、その配偶者は住居費を二重払いすることになります。
そのような場合、標準的な住居費の範囲内で婚姻費用が減額されることがありえます。
しかし、二重払いの事情がない場合、住宅ローンの支払いは婚姻費用には影響しません。
これは住宅ローンは資産形成に資するものであること、住宅ローンより婚姻費用の支払いが優先することが理由とされます。
なお、その他の借金についても基本的には婚姻費用額には影響しません。
3 婚姻費用と夫婦共有財産の持ち出し
一方配偶者が他方配偶者の預貯金を持ち出したような場合、他方配偶者がその預貯金を生活費にあてるべきであり、婚姻費用の支払いは認められないという主張をすることがあります。
しかし、裁判所は、そのような場合でも、持ち出し預貯金を度外視して婚姻費用を決める傾向にあります。
これは持ち出し預貯金の問題は財産分与の問題として処理すれば足りるという考えからです。
この点、札幌高裁平成16年5月31日決定は、「相手方が共有財産である預金を持ち出し,これを払い戻して生活費に充てることができる状態にあり,抗告人もこれを容認しているにもかかわらず,さらに抗告人に婚姻費用の分担を命じることは,抗告人に酷な結果を招くものといわざるを得ず,上記預金から住宅ローンの支払に充てられる部分を除いた額の少なくとも2分の1は抗告人が相手方に婚姻費用として既に支払い,将来その支払に充てるものとして取り扱うのが当事者の衡平に適うものと解する。」として、共有財産の持ち出しがある場合に婚姻費用の支払いは不要としています。
しかし、仙台高裁平成16年2月25日決定は、「婚姻費用分担に先立ち共有財産の清算をすべきである旨主張するが,夫婦間の共有財産の清算は,両者が離婚に至った際に財産分与の形でされるべきものであり,その清算ができなければ,婚姻費用分担ができないという関係にはなく,かえって,相手方が共有財産を当座の生活費のために費消することを前提に婚姻費用分担金を定めることは,後の財産分与の際の法律関係をいたずらに複雑化しかねず,相当でない」として、夫婦共有財産があっても婚姻費用支払義務はなくならないとしています。このような立場が趨勢と思われます。
4 婚姻費用の変更
をご参照ください。
5 弁護士費用
当事務所の弁護士費用は以下のとおりです(消費税別)。
着手金をお支払いいただければ、期日毎にお支払いいただく費用はありません(遠隔地は別途出廷日当が発生する場合があります)
・初回相談料 無料
・離婚交渉 着手金5万円 報酬10万円(財産分与などで経済的利益があるときは、その10パーセントと10万円の大きい方)
・離婚調停 着手金20万円(交渉から引き続き受任した場合の着手金は15万円)
報酬20万円(財産分与などで経済的利益があるときは、その10パーセントと20万円の大きい方)
・離婚訴訟 着手金20万円(調停から引き続き受任した場合の着手金は15万円)
報酬20万円(財産分与などで経済的利益があるときは、その10パーセントと20万円の大きい方)
・婚姻費用調停 着手金20万円(離婚調停と一緒の場合は5万円)
報酬20万円(離婚調停と一緒の場合は5万円)
例 相手方が離婚も婚姻も拒否している場合
交渉の着手時に5万円をいただきます。
話し合いで解決しなければ離婚調停となりますが、その際着手金15万円+5万円=20万円をいただきます。
そこで婚姻費用も、離婚も解決すると、報酬20万円+5万円=25万円を報酬としていただきます。
5 新潟で婚姻費用のご相談は弁護士齋藤裕へ
もご参照ください。
新潟で婚姻費用、離婚でお悩みの方は弁護士齋藤裕にご相談ください。
まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。
弁護士費用はこちらの記事をご参照ください。
さいとうゆたか法律事務所トップはこちらです。

